電車で私の隣に座ってきた男性。突然感じた強烈なにおいで気分が悪くなった理由
公共交通機関に慣れない私にとって、電車という空間はいつも緊張と不安が入り混じる場所でした。思いがけない出来事が、私の「におい」に対する感覚を大きく変えて …
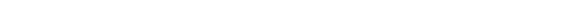
ウーマンカレンダー woman calendar

2018年に『じっと手を見る』、2019年に『トリニティ』が直木賞候補となった窪美澄さん。今年の7月には、短編集『夜に星を放つ』で第167回直木賞を受賞されました。現在、56歳の窪美澄さんは、どのような生活を送りながら、日々、どんな想いで執筆に取り組まれているのでしょうか。インタビュー1回目の今回は、『夜に星を放つ』の収録作品の成り立ちなどを中心にお話を伺いました。
――直木賞のご受賞、おめでとうございます。
窪さん ありがとうございます。
――受賞会見では「まだ実感がない」ということをおっしゃっていましたが、改めて今のお気持ちをお聞かせください。
窪さん 受賞会見から賞の贈呈式まで1カ月ほどあったのですが、時間がピュンと飛んでいるような感覚でした。ありがたいことに、いろいろな媒体さんから取材のご依頼をいただいたりもしていまして、たくさんのことをこなしている間にあっという間に時間がたったという感じです。ですから正直なところ、いまだに「直木賞をいただいた」という実感が湧かないんです。
――シングルマザーとして育て、独立なさった息子さんは、受賞に際してどのような反応をされていたのでしょうか?
窪さん 受賞が決まったときに息子にLINEでメッセージを入れたのですが、仕事の都合でずっと未読だったんです。夜になって再度、「直木賞をいただいたんだけど」とメッセージを送ったら、「えっ!?」という返事が3回ほど続きました。その後、「今、アドレナリンが出まくってすごいんじゃないの?」とメッセージが来たのですが、そんなことはなくて、私自身はすごく冷静だったんですね。息子も受賞を喜んでくれましたし、先日の贈呈式にも来てくれてうれしかったです。
――受賞作『真夜中に星を放つ』には5編の短編が収録されています。1編目の「真夜中のアボカド」の主人公は、コロナ禍にマッチングアプリで出会った恋人がいる女性です。
窪さん 私の年下世代の友人たちが、コロナ禍でマッチングアプリにハマり始めたんです。当時、コロナは今よりもずっと怖い存在でしたし、「この状況でマッチングアプリってどうなの?」って疑問に感じてもいました。
でも、あるとき、ふと「コロナ禍でも人と触れ合いたい、人のぬくもりが欲しいと思うのも当然かもしれない」と思ったんですね。それ以来、マッチングアプリに肯定的になって友人たちの様子を見守っていたんです。「真夜中のアボカド」は、そうした中で思いついたお話です。
――タイトルの“真夜中”にはどんな意味があるのでしょうか?
窪さん 少し前までは新型コロナに対して、今以上に緊張感がありましたよね。ソーシャルディスタンスに神経質になったりなど、緊張しながら仕事や生活をする中で、私自身、真夜中にちょっとだけ解放されるような感覚があったんです。そこから“真夜中”という言葉が出てきたように思います。
――物語は、主人公が育てるアボカドの成長とともに進んでいきます。
窪さん 実際に、私がアボカドを育てているんです。小説家というのは非常に孤独に強い職業ですし、私自身もひとりでいるのは割と平気なほうなんです。
ただ、さすがにコロナ禍が長引くにつれて物寂しい気持ちになったんですね。とはいえ、猫などの動物を飼うのは重く感じられて、植物を育てたいなって思ったんです。私はよく、朝食でアボカドを食べているので、その種を育ててみることにしました。
――物語の中では、種から根が生えるなどアボカドの変化がつづられています。
窪さん アボカドの種から根っこが出てきたり、双葉が生える様子を見ていると植物と共存しているような気持ちになりました。かなりゆっくりなペースではあるのですが、気付くと大きくなっていて、今は50㎝くらいの高さにまで成長しています。
あなたの体験談も教えて! 抽選でギフト券進呈

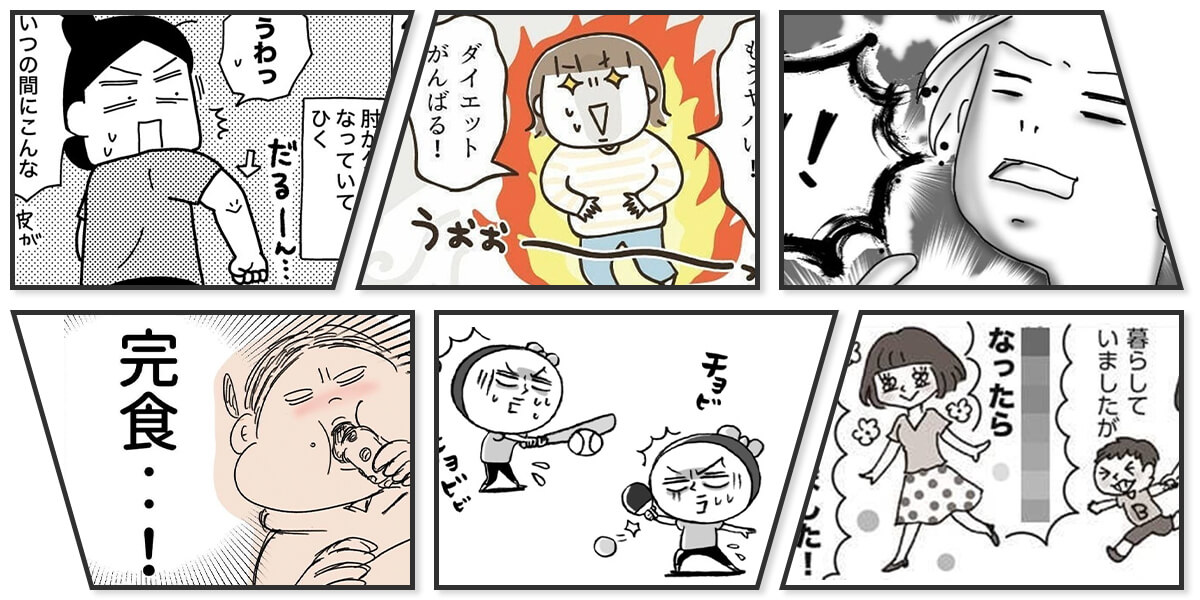




































































































2児の母のはたりさんによる、保育園で遭遇した体験談を描いたマンガ。バリキャリのすーちゃんママはいつも忙しそうですが、身だしなみは完璧。その夫から、彼女と比較され身だしなみや家事のや...
続きを読む2児の母のはたりさんによる、保育園で遭遇した体験談を描いたマンガ。すーちゃんママはバリキャリで、いつも身だしなみが完璧。その夫は、はたりさんことチロちゃんママたちの身なりや家事の仕...
続きを読む2児の母のはたりさんによる、保育園で遭遇した体験談を描いたマンガ。バリキャリでいつも完璧なすーちゃんママ。その夫は、保育園のママたちの身だしなみに口を出し、化粧もマナーの1つなどと...
続きを読む2児の母のはたりさんによる、保育園で遭遇した体験談を描いたマンガ。バリキャリでいつもきれいなすーちゃんママの夫は、はたりさんことチロちゃんママたちに向かって「なぜ身だしなみを気にし...
続きを読む2児の母のはたりさんによる、保育園で遭遇した体験談を描いたマンガ。保育園の懇談会でのこと。バリキャリでいつもきれいなすーちゃんママの夫が、ママたちに「なぜ身だしなみを気にしないの?...
続きを読む公共交通機関に慣れない私にとって、電車という空間はいつも緊張と不安が入り混じる場所でした。思いがけない出来事が、私の「におい」に対する感覚を大きく変えて …
私は大手商社で営業職に就いています。足が棒になるまで取引先を回って新規顧客を獲得するのが使命です。実は私はわが社で唯一の中卒。学歴について肩身の狭い思い …
55歳からマンガを描き始めたナランフジコさんによる、熟年夫婦の生活を描いたマンガ。 フジコさんにとっては久しぶりのライブで、夫にとっては人生初のライブ観 …
年を重ねると、筋力や体力の低下を感じやすくなるもの。実は気付いていないだけで、内臓も加齢とともに機能が低下していきます。特に「腎臓」の機能低下はさまざま …
今の夫と付き合っていたころの話です。私たちは一度別れてから、再び復縁して付き合い始めました。 目次 1. 復縁後の初旅行 2. 旅行当日に美容室へ!? …
実家に帰って久しぶりに再会した弟から「老けたね」と言われ、ショックを受けた私。鏡に映った当時42歳の自分の姿を見てがくぜんとしました。そんな出来事がきっ …
イラストレーター&漫画家のフカザワナオコさんによる、アラフィフ女子の日常を描いたマンガ。今回は思いがけずうれしかったことについてお届けします。 …
長女が自分から「これがいい」と言った、初めてのお子さまセット。ワクワクしたのもつかの間、親の想像を軽く飛び越えていく展開に、私はただただ反省するばかりで …